ラウンドテーブル vol.6「申請書って結局何を書けばいいの?〜文化芸術活動の社会性・公共性を言語化する〜」の開催について
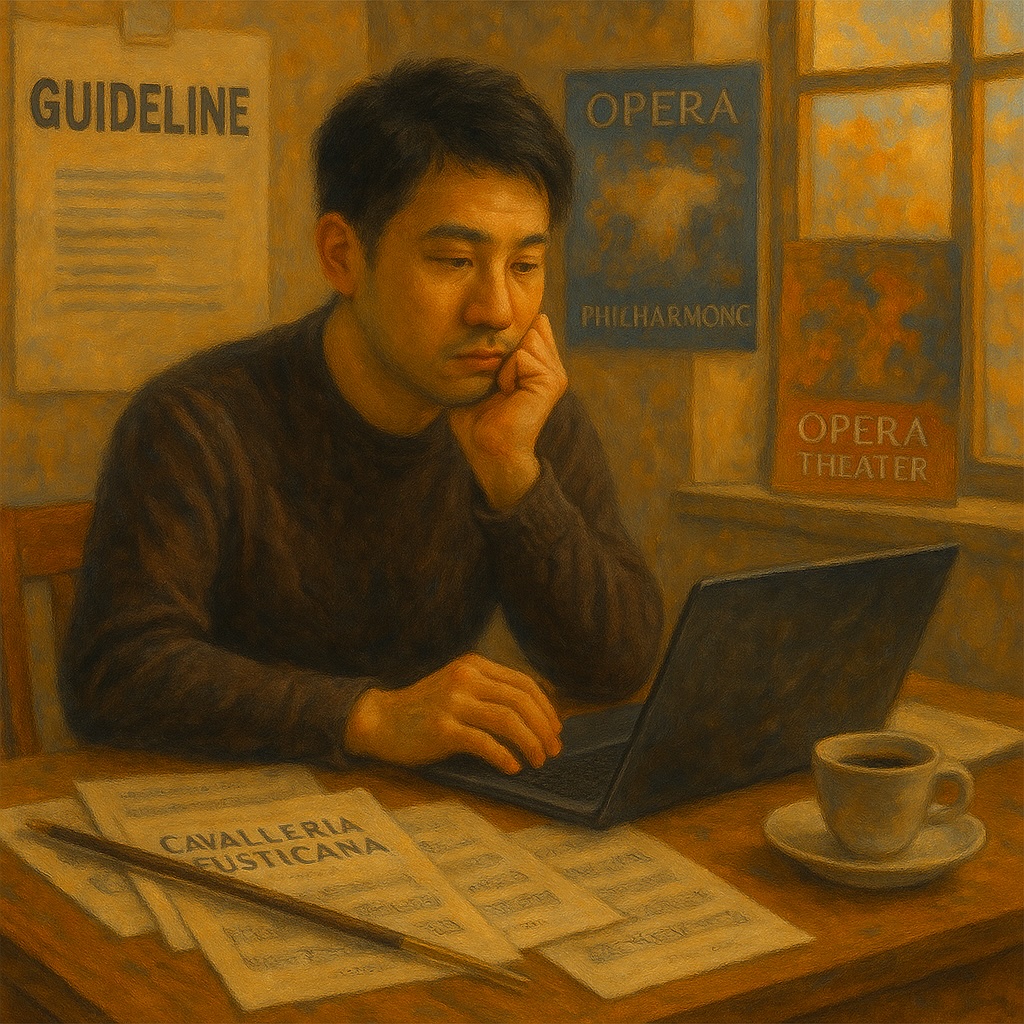
ラウンドテーブル vol.6「申請書って結局何を書けばいいの?〜文化芸術活動の社会性・公共性を言語化する〜」
日時:令和7年10月21日(火)19:00~20:30(受付開始:18:45~)
会場:大阪府立江之子島文化芸術創造センター 2階 ルーム8
(大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-34)
スピーカー:宮崎優也(大阪アーツカウンシル 統括責任者)
参加費:無料
定員 :20名(当日、先着順に受付を行います)
助成金や補助金の申請書を書くとき、多くの方が一度は「結局、何を書けばいいの?」と悩まれるのではないでしょうか。
かつては「芸術が好きだから応援する」という情熱だけでも支援が成り立つ時代がありました。しかし今では、企業や財団など支援する側から「なぜその活動を支援するのか」という説明が求められるようになっています。
そのため、アーティスト固有の創造性だけでなく、「公共的な価値」や「社会的なインパクト」といった側面からも語ることが必要になってきました。
こうした流れに戸惑いやモヤモヤを感じる方も多いと思いますが、一方で、行政や企業・財団などは社会にどんな成果や広がりをもたらすのかを期待しています。
大切なのは、「支援者が求める分かりやすさ」と「芸術が本来持つ豊かさや曖昧さ」をどう橋渡しするか。その工夫のなかに、活動の魅力を言葉にし直すヒントが隠れています。今回のラウンドテーブルでは、申請書づくりを単なる“義務”としてではなく、新しい観客や支援者と出会うチャンス、「創客」につながる言葉を見つける場にしたいと考えています。
※障がい等により配慮を希望される場合は、事前に下記のお問合せ先までご相談ください。
本イベントについてのお問合せ先:
大阪アーツカウンシル info@osaka-artscouncil.jp
スピーカー
スピーカー:宮崎 優也(みやざき ゆうや)

指揮者
1988年東京都生まれ。高校卒業後に渡米し、指揮・音楽学・神経心理学を学ぶ。ノーステキサス大学大学院で音楽修士号を取得後、博士課程単位取得満期退学。指揮を David Itkin、Dian Tchobanov、Gregory Buchalter、Tomáš Netopil、村方千之、作劇法を Steven Dubey、音楽学を Peter Mondelli に師事。米国で11年間活動し、オーケストラやオペラ、教育分野で経験を重ねた。帰国後は国内のオペラ団体やフリーランスの指揮者として活躍し、堺シティオペラのアーティスティックディレクター兼事務局長を経て、現在は大阪アーツカウンシル統括責任者、日本芸術文化振興会プログラムオフィサー(音楽分野)、龍谷大学国際学部非常勤講師(音楽芸術論)を務める。演奏・教育・研究・政策を横断し、芸術の本質と社会を結ぶ活動を展開している。
助成金や補助金の申請書を書くとき、誰もが一度は「結局、何を書けばいいの?」と悩むのではないでしょうか。
活動の目的も、想いも、芸術の価値も頭の中にははっきりあるのに、いざ言葉にしようとするとどう書けば伝わるのか分からない。
私自身、これまで何度もその壁にぶつかってきました。
どうしても、申請書を書くときには「自分の活動」や「自分の表現」という内側の視点になりがちです。
けれど、助成や補助の仕組みは、支援者や市民の理解と共感によって支えられています。
つまり、そこには“支援する側の視点”や、“文化芸術を受け取る側の視点”も同時に存在しているんです。
これは決して「芸術を大衆に迎合させる」という話ではありません。
むしろ逆に、なぜ芸術が支援されるべきなのか、なぜその活動が社会にとって必要なのかを俯瞰して考えることが、
芸術の本質的な価値をより豊かに、説得力をもって伝えることにつながります。
そして、それは単に「助成金を取るための技術」ではなく、
まだ自分の活動に触れたことのない人たちと新しい接点をつくり、
“創客”――つまり新しい観客や共感者を生み出すための第一歩でもあります。
私は指揮者として舞台に立ち、制作側として公演を企画・運営し、
またアーツカウンシルや審議会の立場から申請書を読み、審査や評価に携わってきました。
創る側、支える側、そして社会の側――その三つの視点を行き来して見えてきたことがあります。
それは、「言葉を整えること」は決して芸術性を削ぐものではなく、
芸術の力を社会に橋渡しする“翻訳”のような作業だということ。
今回のラウンドテーブルでは、そんな視点を共有しながら、
皆さんと一緒に“伝わる言葉”を考えたいと思います。
申請書を“義務”ではなく、“未来の共感を育てるツール”に――
そんな時間になれば嬉しいです。
宮崎
大阪アーツカウンシル オープンオフィス vol.6
日時:令和7年10月21日(火)14:00~18:30
会場:大阪府立江之子島文化芸術創造センター 2階 ルーム8
(大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-34)
参加費:無料
ご予約:不要(事前予約の方を優先してご案内いたします)
*ご相談をご希望の方は、事前に申込者のお名前、所属団体、相談内容、希望する時間帯を明記の上、メールでinfo@osaka-artscouncil.jp までご連絡ください。調整の上、予約を確定いたします。
なお、当日19:00~20:30には、「申請書って結局何を書けばいいの?〜文化芸術活動の社会性・公共性を言語化する〜」と題し、文化芸術関係者の皆様とともに、文化芸術活動の企画書や申請書の書き方について考えるラウンドテーブル(座談会)を開催いたします。どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。
